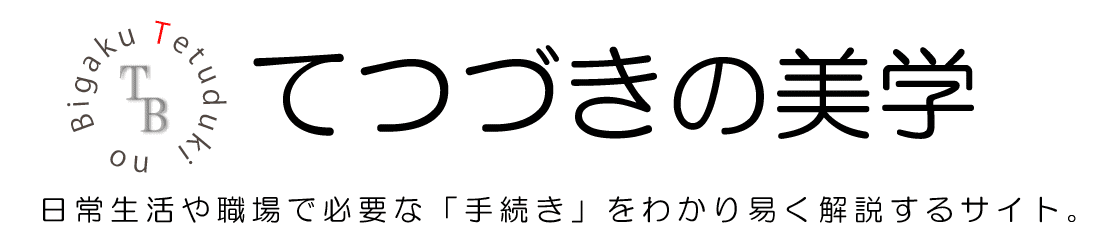退職後の健康保険は「国民健康保険に加入する」・「任意継続に加入する」・「扶養に入る」3つの選択肢がありますが、扶養に入れない場合は、「国民健康保険」か「任意継続」のどちからかに加入する必要があります。
国保に加入するか?任意継続にするか?どちらか迷っている人の中には、『保険料次第!』という人が多いと思います。
そこで今回は、国民健康保険と任意継続(協会けんぽ)の保険料(令和5年度)を、年収別に比較してみましたので、保険料で迷っている方がいたら参考にしてみてください。
※任意継続の加入期限は退職日の翌日から20日以内です。また、一度、国民健康保険に加入してしまうと任意継続には加入できなくなりますので、ご注意ください。
任意継続と国民健康保険の保険料を比較
今回は、『協会けんぽ東京都の保険料額(令和5年度)』と『東京都世田谷区の国民健康保険料(令和5年度)』で計算した保険料で比較をしています。
(※任意継続保険料は各都道府県ごとに異なり、国民健康保険料(税)は各市区町村ごとに異なりますのでご注意ください。)
また、今回は、任意継続と国民健康保険の保険料を「加入者本人のみ(扶養家族のいない人)の場合」と「被扶養者(収入0円の妻と子※)2人がいる場合」を別々にまとめまて比較していますので、ご自身のケースに近いものを参考にしてみてください。
※令和4年4月から未就学児(0歳~6歳)の国民健康保険料が減額されていますが、今回の比較では6歳~の子を対象に計算しています。
年収240万円・標準報酬月額20万円の人のケース
加入者本人のみ(扶養家族のいない人)の場合
まず、任意継続の保険料から確認していきましょう。
<任意継続保険料>
保険料の調べ方については、こちらの記事で詳しく解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶退職後の健康保険「任意継続」保険料の調べ方と加入方法を解説
標準報酬月額20万円の保険料は、次のとおりです。
続いて、国民健康保険料を確認していきましょう。
<国民健康保険料>
年収240万円の人の国民健康保険料は、次のとおりです。
比較すると、「任意継続より国保の方が保険料が安い!」という結果になりました。
被扶養者(収入0円の妻と子)2人がいる場合
<任意継続保険料>
任意継続の場合は、被扶養者の保険料は無料なので、先程の本人のみの保険料と同じです。
続いて、国民健康保険料を確認していきましょう。
<国民健康保険料>
国民健康保険には扶養という概念がないため、無職の人(専業主婦や子ども)でも保険料が発生します。
▶国民健康保険料の計算方法、収入のない妻や子供の保険料も確認!
今回の比較では「任意継続の方が保険料が安い!」という結果になりました。(国保軽減を受けた場合を除く)
年収360万円・標準報酬月額30万円の人のケース
加入者本人のみ(扶養家族のいない人)の場合
<任意継続保険料>
下の標準報酬月額表から任意継続の保険料を確認していきます。
任意継続の保険料には上限(標準報酬月額30万円)が設定されていますので、標準報酬月額30万円以上は「標準報酬月額30万円の保険料」となります。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶退職後の健康保険「任意継続」保険料の調べ方と加入方法を解説
標準報酬月額30万円の場合の保険料は、次のとおりです。
続いて、国民健康保険料を確認していきましょう。
<国民健康保険料>
年収360万円の人の国民健康保険料は、次のとおりです。
今回は「任意継続より国保の方が保険料が安い!」という結果になりました。
被扶養者(収入0円の妻と子)2人がいる場合
<任意継続保険料>
任意継続の場合は、被扶養者の保険料は無料なので、先程の本人のみの保険料と同じです。
続いて、国民健康保険料を確認していきましょう。
<国民健康保険料>
今回は、年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない)の場合国保の方が安く、年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない)の場合は任意継続の方が安いという結果になりました。(国保軽減を受けた場合を除く)
年収600万円・標準報酬月額47万円の人のケース
加入者本人のみ(扶養家族のいない人)の場合
<任意継続保険料>
下の標準報酬月額表から任意継続の保険料を確認していきます。
任意継続の保険料には上限(標準報酬月額30万円)が設定されていますので、標準報酬月額30万円以上は「標準報酬月額30万円の保険料」となります。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶退職後の健康保険「任意継続」保険料の調べ方と加入方法を解説
標準報酬月額47万円の場合の保険料は、次のとおり(標準報酬月額30万円の保険料)となります。
続いて、国民健康保険料を確認していきましょう。
<国民健康保険料>
年収600万円の人の国民健康保険料は、次のとおりです。
今回の比較は「国保より任意継続の方が保険料が安い!」という結果になりました。
被扶養者(収入0円の妻と子)2人がいる場合
<任意継続保険料>
任意継続の場合は、被扶養者の保険料は無料なので、先程の本人のみの保険料と同じです。
続いて、国民健康保険料を確認していきましょう。
<国民健康保険料>
国民健康保険には、扶養という概念がないため、無職の人(専業主婦や学生)でも保険料が発生します。
今回の比較も「国保より任意継続の方が保険料が安い!」という結果になりました。
まとめ
最後に、任意継続と国保の特徴と今回の比較についてまとめてみました。
<任意継続の特徴>
任意継続は、保険料に上限が設定されているため、在職中にもらっていた給与が多ければ多い人ほど保険料がお得になり、国保より保険料が安くなる場合があります。
<国民健康保険の特徴>
国保の場合、在職中にもらっていた給与が多ければ多い人ほど保険料が高くなり、家族がいる場合はその人数分の保険料もかかるので、任意継続の方がお得になるケースもありましたね。
<今回の比較まとめ>
加入者が本人のみの場合は、年収500万円前後が分岐点の目安になると思います。
年収500万円以下の場合は国保の方が安く、年収500万円以上の場合は、任意継続が保険料が安くなる計算です。
また、被扶養者(収入0円の妻と子)2人がいる場合は、年収240万円前後が分岐点の目安になると思います。
年収240万円以下の場合は国保の方が安く、年収240万円以上の場合は、任意継続が保険料が安くなる計算です。※お子さんの年齢が0歳~6歳(未就学児)でない場合
(※各保険料は都道府県・市区町村で異なるため、どちらもあくまで目安として参考にしてください。)
ただし、国保の『軽減』が利用できる場合は、ダントツ国保が有利です!
会社を辞めた理由によっては『軽減制度』を利用できる場合がありますので、よろしければこちらで条件等を確認してみてください。
▶国保の軽減:失業したときの保険料はいくら?計算方法と申請方法を確認